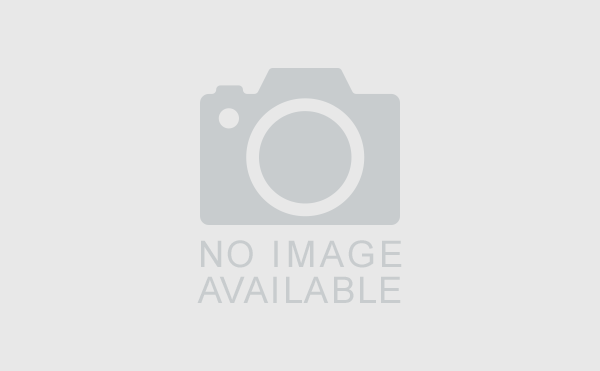高額療養費制度とは?

先生、高額療養費制度って何ですか?名前は聞いたことあるんですけど…。

高額療養費制度というのは、簡単に言えば「医療費が高額になったときに、自己負担がある程度までで済むようにする制度」のことです。
例えば1か月の医療費の自己負担額(病院の窓口で払うお金)が、あらかじめ決められた上限額を超えた場合、その超えた分を後から健康保険が負担してくれます。
上限額は年齢や所得によって異なりますが、誰でも「1か月にこれ以上は払わなくていい」という金額が決まっているんです。

上限額があるおかげで、治療費がものすごく高くなっても全部払わなくていいんですね。

そうです。この制度のおかげで、重い病気や大きな手術で医療費が数百万円かかっても、患者さんの窓口負担は高くても数万円程度で抑えられます。
例えば中所得の方の場合、月に100万円の医療費がかかっても、自己負担はおよそ8万7,000円程度で済みます。
このように高額療養費制度は、患者さんや家族の医療費負担が重くなりすぎないようにする「セーフティネット(安全網)」としての役割を果たしているんですよ。

家計が助かる仕組みなんですね!でもどうしてこんな制度があるんでしょう?最初から3割負担とかにしてるのに…。

日本ではもともと、みんなが医療保険に入って医療費の一部(通常3割)を負担する仕組みですが、それでも月に何十万円もの自己負担が発生すると生活が立ち行かなくなる恐れがあります。
そこで1973年にこの高額療養費制度が始まりました。
開始当初は、一旦全額を支払った後で超えた分が払い戻される方式でしたが、2007年からは事前に上限額までしか払わなくて済むよう改良されています。
つまり、患者さんは上限額までのお金さえ用意すればよく、それ以上は払わなくていい仕組みになったんです。
こうした制度のおかげで、「お金がないから治療を諦める」
という事態を防ぐことが目的なんですね。
今回の見直し案とは?

最近この高額療養費制度を見直すってニュースで聞いたんですけど、何をどう変えようとしていたんですか?

政府が検討していた見直し案は、患者の自己負担の上限額を引き上げるという内容でした。具体的には、2025年8月から段階的に(月額の)負担上限を引き上げ、2027年8月までに3段階で新しい上限額にする計画です。
ポイントをまとめると次の通りです。
- 上限額の段階的な引き上げ: 現行制度では例えば70歳未満・年収約370万~770万円の方の自己負担上限は約8万円ですが、2025年8月にまず約8万8,000円に上げ、さらに2027年8月までに最終的には約13万9,000円前後にまで引き上げる案。
最大で現在より73%ほど上限額が増える計算。収入が高い人ほど負担増が大きくなるよう設定され、逆に低所得者の上限引き上げ幅は小さく抑える方針。 - 頻回利用者の優遇措置の見直し: 高額療養費制度には、「多数回該当(たすうかいがいとう)」といって、1年間に3回以上高額療養費の世話になった場合4回目から上限額がさらに下がる仕組みがある。現行では年収約770万円以下の人なら4回目以降の上限は約4万4,400円に抑えられる。見直し案ではこの優遇措置(4回目以降の上限額)も引き上げる予定。つまり長期治療が必要な患者さんの負担軽減策を縮小する方向だった。

月8万円だった上限が将来的には14万円近くまで跳ね上がる…かなり思い切った改正ですね。それだけ患者の負担が増えるわけですよね?

その通りで、大幅な負担増になります。政府はこの見直しによって健康保険財政を安定させ、現役世代(働く世代)が払う保険料の急上昇を抑えたい考えでした。高齢化や高額な新薬の登場で、高額療養費制度にかかる国全体の費用が年々増えていて、何もしないと保険料が上がってしまう。
例えば見直しを全部やめてしまうと、現役世代では年間3,000〜4,200円程度、保険料が余計に上がるという試算も示されています。
そうした背景から、「上限額を上げてでも制度の持続性を確保しよう」というのが当初の政府方針でした。

財政のために患者の自己負担を増やすわけですね…。でもそれに患者団体などが反発したと聞きました。

はい。見直し案が明らかになると、がん患者さんや難病患者さんの団体などから「負担増は困る」「命に関わる問題だ」という強い懸念の声が上がりました。
年末の予算編成で政府がこの方針を決めた後、昨年末から今年にかけて患者団体が厚労大臣宛てに要望書を提出したり、声明を出したりしています。
例えば全がん連(全国がん患者団体連合会)は「高額療養費の上限引き上げをやめてほしい」と要望書を出しましたし、多くの医学会も患者側を支持する声明を発表しました

患者さん側からすれば、負担が急に増えるのは本当に死活問題ですよね…。


患者さん不在の拙速な議論だったんですね…。それで最終的に凍結になったとか?

はい、こうした反発を受けて政府も方針転換を余儀なくされました。2025年度予算の国会審議の中で野党も「負担引き上げの凍結」を強く求め、最終的に政府はこの見直し案の実施を一時凍結することを決めたんです。
特に長期療養される患者さんへの影響が大きい「多数回該当」の見直し(4回目以降の負担増)は行わず現行通り据え置く、と明言しました。
結果として、8月から予定されていた負担上限の引き上げは当面ストップする方向になったわけです。

凍結が決まったのは良かったですけど、部分的な凍結という話も聞きました。全部やめるわけではないんですか?


実は政府内でも当初は「全部を凍結するのは難しい」という声があり、一部のみ凍結(多数回該当の部分だけ据え置き)という対応が示されました。しかしそれでは「焼け石に水」(対象者は高額療養費利用者の2割程度しかおらず不十分)との批判も強く、最終的には見直し案自体を当面実施しない方向で最終調整されたようです。
政府・与党が「一旦立ち止まって考える」と判断した背景には、やはり患者さんや世論の反発を無視できなかったということですね。凍結というのは「今回は見直しを見送るが、将来的にまた議論するかもしれない」という意味合いです。
具体的な生活への影響

もし見直し案が実施されていたら、あるいは将来実施されたら、私たちの生活には具体的にどんな影響が出るんでしょうか?

一番直接的なのは医療費の自己負担額への影響です。高額な医療を受ける場合、患者さんの支払い上限が上がるので、これまでより多くのお金を用意しなければならなくなります。
例えば月に50万円の抗がん剤治療を受けている方なら、現行では自己負担は約8万円ですが、見直し後はそれが数万円単位で増えるわけです。以下、考えられる影響を整理してみましょう。
- 患者への経済的負担増: 長期の治療が必要な患者ほど負担増が大きく、貯金の切り崩しや借金に頼らざるを得ないケースも出てきます。収入や蓄えが少ない人は治療の継続自体が難しくなりかねず、必要な医療を諦めるリスクが指摘されています。
実際「命に関わる問題」という声も上がったほどで、病気とお金の二重の不安を抱えることになります。 - 高齢者・重病者ほど影響大: 特にがん患者や難病の方、人工透析を受けている方など、毎月のように高額療養費制度に頼っている層には深刻です。これらの方々は多数回該当の仕組みで負担が抑えられていましたが、その上限引き上げが行われれば毎月の支払いが増えてしまいます。高齢の方でも現役並み所得(収入がある程度高い層)の場合は上限引き上げ対象になるので、年金生活への打撃にもなりえます。
- 健康保険料への影響: 一方で見直し案を凍結したままにすると、医療保険財政の負担は増え続けます。そのツケは保険料の値上げとして国民全体に広く及ぶ可能性があります。政府試算では見直しをしない場合、後期高齢者(75歳以上)で年額約1,000円、現役世代では年額3,000〜4,200円ほど保険料が上がるとされています。凍結により患者さん個人の負担増は避けられますが、医療費全体を皆で支えるコストは増えるという側面もあるんですね。
- 心理的な安心感: 高額療養費の上限が据え置かれれば、「万一大病してもこの金額までの負担で済む」という安心感があります。しかし上限額が引き上げられると、「もし病気になったら○○万円も払わないといけないのか…」という不安が大きくなります。特に若い世代でも、将来親の介護や自分の病気で大金が必要になる不安が高まれば、消費を控えたり治療を先延ばしにしたりする行動変容につながるかもしれません。
医療費負担の見通しが立たないと、安心して生活できないという声もあります。

本当に生活に直結する問題なんですね。負担増になったら治療費を工面するのに奔走しなきゃいけないし、保険料が上がるのも困るし…。

患者さんにとっても国民全体にとっても痛みを分かち合う話なので、どこに負担を求めるかという難しい問題です。見直し案が実施されていたら、一部の患者さんは治療費のために毎月数万円の負担増となり、家計を切り詰めたり支援を求めたりしなければならなかったでしょう。
逆に凍結されたことで当面は負担増を心配しなくて済みますが、今度は医療保険財政の課題が残ります。ですから「誰かの負担を減らすと別の誰かの負担が増える」というトレードオフの関係にあるといえますね。いずれにせよ、制度変更が私たちの生活に与える影響は大きく、他人事ではないということです。
過去の変更例と比較

高額療養費制度って今までにも改正されてきたんですか?今回が初めてではないですよね。

はい、これまでも時代に合わせて何度か見直しが行われています。主な変更点をいくつか挙げてみましょう。
- 1973年 – 高額療養費制度の開始。それまで家族(被扶養者)の医療費負担は一部定額給付でしたが、1か月3万円を超える部分を支給する制度としてスタートしました。
「福祉元年」と呼ばれる年で、社会保障充実の一環でした。同時に被扶養者の医療給付割合が5割から7割に引き上げられています。
開始当初は後から払い戻す方式で、患者は一旦全額を支払う必要がありました。 - 1980年代 – 患者本人(被保険者)にも高額療養費制度が適用されるよう拡大されました(1981年)。また自己負担が定率化(一定割合負担)される改革に伴い、上限額の設定や見直しが行われています。1983年には最初の上限額引き上げがありました。その後も物価や医療費の増加に応じて上限額は改定されています。
- 2007年 – 大きな制度改善として現物給付化が行われました。
それまでは高額療養費は払い戻し制でしたが、2007年以降は事前に「限度額適用認定証」を発行してもらえば、窓口で上限額までの支払いで済むようになりました。
これにより高額な治療の際にも最初から自己負担は上限額までで抑えられ、患者の手続き・金銭負担が大幅に軽減されました。 - 2015年 – 最近の大きな改正は平成27年(2015年)1月です。この時は70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化され、それに応じて自己負担限度額もきめ細かく設定されるようになりました。
具体的には高所得者層の区分を増やし、収入に応じて負担上限がより高くなるよう変更されています。例えば改正前は月額上限が一律だった「一般所得者」の区分が細分化され、収入が多い人は上限額が引き上げられました。逆に低所得者の区分では据え置きや減額も行われ、負担能力に応じた制度へと調整されています。 - 2017年 – 70歳以上の高齢者についての特例措置(外来特例)の見直しが始まりました。それまで70歳以上は外来医療の自己負担上限が低めに設定されていましたが、医療費増大への対応として2017年8月から段階的に上限額を引き上げています。
(※69歳以下の上限額は当時変更なし)。現役並み所得の高齢者は3割負担ですので、その方々の月額上限が引き上げられた形です。

こうして見ると、昔から少しずつ制度を調整してきたんですね。2015年に区分細分化とか、直近だと高齢者の負担見直しも…。今回の案は2015年以来の大きな改正になる予定だったんでしょうか?

そうですね。実は2015年以降、約10年間この制度の見直しは行われてきませんでした。
その間に医療費の状況は大きく変化していますから、今回は久々の大きな改正になるはずでした。特に患者の負担上限額自体をこれだけ大幅に引き上げるのは、制度創設以来でも異例の規模です。過去の改正では高所得者の負担増など部分的な調整が多く、一般の患者さん全体にここまで広く負担増が及ぶ改定は初めてと言っていいでしょう。そういう意味でも今回の見直し案は非常にインパクトが大きく、だからこそ反発も強かったといえます。

なるほど…。過去にも負担増の改定はあったけど、今回は桁違いだったわけですね。

はい。例えば1980年代や2015年にも上限額の変更はありましたが、段階的で比較的緩やかなものでした。高額療養費制度は「社会全体で支える」仕組みなので、バランスを見ながら少しずつ手直しされてきた歴史があります。今回のように一度に何割も負担を増やす案は極めて踏み込んだ変更だったので、過去と比較しても異例と言えるでしょう。過去の例から学べるのは、制度変更には国民の理解と慎重な手続きが必要だということですね。
今後の見通し

凍結されたとはいえ、医療費の問題自体は解決していないですよね。この先、高額療養費制度はどうなっていくんでしょう?

おっしゃる通りで、問題は先送りになっただけです。今後の見通しとしては、改めて制度の在り方を議論し直す場が設けられると考えられます。政府も「一番苦しんでいる方々の声を聞かずに制度を決めてはいけない」と反省を示しています。
実際、総理大臣(当時)は厚生労働大臣に対して、患者など当事者の意見を踏まえて制度を検討し直すよう指示しました。
ですから今後は患者代表や専門家の声をきちんと聞きながら、より納得感のある見直し案を作る努力がなされるでしょう。

制度を維持するには見直し自体は避けられないんでしょうか?やっぱり将来的には上限を上げたりするんですかね…。

国の医療費財政を考えると、ある程度の見直しは避けられないというのが現実です。超高額の新薬(例:1千万円を超えるような治療)も登場していますし、少子高齢化で現役世代の負担も限界があります。
そのため「負担できる人には少し多く負担してもらい、弱い立場の人は守る」という方向で落とし所を探ることになるでしょう・
例えば、今回の凍結で据え置かれた多数回該当(長期療養者の優遇)は今後も維持しつつ、所得が高い層の上限額だけ段階的に引き上げる案などが考えられます。
実際、見直し案でも低所得者や長期療養者への配慮が議論されていたように、メリハリをつけた改定なら受け入れられる可能性があります。

なるほど、全員一律に上げるんじゃなくて、負担に差をつけるわけですね。

はい。他にも公費(税金)でどこまで支えるかという議論も必要になるかもしれません。
高額療養費は基本的に保険料で賄われていますが、極めて高額な医療は国が別途助成する仕組みを作るとか、医療費全体の無駄を減らして財源に充てるとか、いろいろ改善の余地はあります。重要なのは、患者さんが安心して治療を受けられ、かつ制度が持続可能であるバランスを見つけることです。

患者の声を反映しつつ、持続可能性も確保する…難しい課題ですね。

おっしゃる通りです。今回の凍結で得られた教訓は、「当事者の声を無視した拙速な改定はうまくいかない」ということでした。
今後は患者団体や国民への丁寧な説明と合意形成が不可欠でしょう。制度の改善点としては、例えば情報提供の強化も挙げられます。
高額療養費制度自体、まだ十分に知られておらず、本来なら払い戻しを受けられるのに手続きを知らない人もいます。
そうした周知を進めつつ、無理のない範囲で制度を調整していくことが理想ですね。

私たちも制度について正しく知って、声を上げていくことが大事なんですね。今日はとても分かりやすかったです。
ありがとうございました!

こちらこそ、最後まで聞いてくれてありがとうございました。高額療養費制度は誰にとっても他人事ではないので、ぜひ関心を持ち続けてくださいね。